『苺は大好きな恋人と一緒にお風呂に入りたいようです。』
KindleDirectPublishing『恋の魔法に失敗して意地悪な弁護士さんに発情してしまう苺のお話』
のSNSフォロー特典のショートストーリーになります。本編はこちらから どうぞ!
※18禁表現が含まれます。未成年の方、性的表現が苦手な方の閲覧はご遠慮下さい。
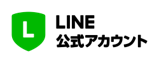



恋の魔法に失敗して、「意地悪な弁護士さん」が「優しい恋人」になりました。それから八か月が過ぎて真夏の夜―――
「………んっ、ん、あぁ……っ、―――」
照明を落とした部屋の、ベッドの上。快感にのたうつ腰を掴まれ、突き上げられる度に亜希は甘い声を零した。
「ゆーきさん、………っ、も、…………」
薄っすらと目を開け、哀願する。絶頂が近い。繋いだ手が彼の口元まで掲げられ、指先にキスを貰う。
「もう少し頑張れよ。あと五回突くから我慢な」
「イヤ、も、無理だから……、も、も、むり…………っ」
イヤ、と繰り返すのに、ずん、と下からいっそう力強く、深く突き上げられて、亜希の体が大きく弾む。ぎりぎりのところで、達するのを堪えた。
「んんっ………、や……っ、ゆーきさん、おねが………」
「いい子だ、我慢出来た。あと四回」
「あああ、あっ」
亜希は震える手で切ない涙を流す性器の根元を押し包んだ。けれど、恥ずかしいくらい感じやすい秘密の凝りをさらにもう一度、恋人の情欲で甘く擦られ、いじめられて、どうしようもなく体が痙攣した。背中が反り返り、甘い、甘い苺のような瞬間が訪れる。
「あっ………―――、あ―――……」
恋人の腕の中で、亜希は歓喜に打ち震えた。緊張した下肢から一息に亜希の衝動が放出され、その官能に薄い背中が仰け反る。そして解放感が訪れた。大好きな恋人の腕の中で幸福感に満たされて、亜希は荒い呼吸のまま汗ばんだ額を結城の肩口に擦り付ける。
「………ん、ん」
そうして脱力した体をもう何度か揺すられて、結城の熱を受け止める。「あと五回」、を守れなかったけれど、結城はご褒美のように小さなキスをくれた。恋人が自分の中で極まることは、先ほどとは違う幸せを亜希にもたらす。
幸福な睦み合いが終わったばかりの二人分の呼吸が薄暗い部屋に響いていた。下肢ではまだ繋がったまま上半身を少し離して、つむじと、こめかみ、目尻、そしてまた唇にキスをされる。互いが味わった快感を味見をするみたいなキス。
亜希からも首を擡げておずおずとキスを返すと、彼がずるりと出て行った。
「んっ………」
かすかな違和感に眉根を寄せると、結城が誘った。
「風呂に行こうか。たまには一緒に入ろう」
「……やだ」
「どうして。汗かいたし疲れたろ? 最後までちゃんと面倒見るよ」
汗もかいたし、色んな体液で下肢が濡れているから、もちろん体を洗い流した方がいい。体をきれいにした方が気持ち良く眠れる。それは分かる。………でも。
「大丈夫だよ、お風呂くらい、自分で入れるから」
「セックスの後で恋人とばらばらに風呂に入るなんて愛想も色気もないよ。だいたい何でセックスするのが平気で風呂に入るのがダメなんだ。セックスの方が過激な行為なんじゃないのか?」
「そうだけど、……だって、この部屋は薄暗いからいいけど、お風呂は明るいし、だから、やっぱりは、は、はず……」
恥ずかしい、ということはとても恥ずかしい。
彼の腕の中はとても居心地がいいのに、少し体を離して全身が彼の視線に晒されると、途端に身の置き所がなくなる。ちゃんと食べるようになったとはいえ、まだ体は頼りなく薄べったい。浴室の明るい照明の下で見られるなんて恥ずかしくて耐えられない。
結城は、指で、唇で、亜希の体を大切な宝物のように触れてくれる。彼が亜希の全部を心から愛おしいと思ってくれていることは、多分、分かっているのだけれど、それとこれとは話が違うのだ。
「分かった。じゃあ俺は目を閉じておくからいいだろ? 絶対に見ない。お前が恥ずかしがって嫌がるようなことは絶対にしない。約束する」
「…………でも」
「まあ、見えないから変なところを触ったとしても怒るなよ」
にやっと笑って破廉恥なことを口にする結城に、亜希はとうとう怒った。
「もー! やだったらヤダ! そんなことばっかり言うなんて結城さん、オヤジだよ!」
「オヤジはひどいな、ノエルと一歳しか変わらないぞ」
大好きな義兄の名前が出て、つい怯んだが、でも負けない。
「にーちゃんは俺に変なこと言わない。オヤジは、エッチでスケベだからオヤジなんだよ! オヤジは嫌いだから、俺は、お風呂は一人で入るの!」
亜希の必死の抵抗に、結城が吹き出す。
「高校生にオヤジだって言われたらもう否定出来ないな。分かった、今日は諦めて一人で寂しく入るよ」
結城は降参の意味で両手のひらを見せて肩を竦めた。そして亜希に先に風呂を譲ってくれた。その間に、シーツを替えておくよとまたおでこにキスをくれた。
一人で浴室に向かい、シャワーを浴びて、亜希は何だかちょっと後悔してしまった。
『魔法』の失敗で、結城との恋人にしてもらって八か月。その間にお風呂を廻って何度か結城と争っている。その度に結城は笑って折れてくれる。 恥ずかしい、ことはもちろんだが、今更、じゃあ一緒に入ると言うのも何だかいっそう恥ずかしいのだ。
「………バカだったかも……」
亜希は湯船の中、膝を抱いて呟いた。 寧ろ、そういうことをしてみたいと思っているのは、亜希の方なのに。
恋人と一緒にお風呂に入る。泡をたくさん立てて、お互いの体をくるくるに洗うのは子供の遊びみたいできっと楽しいに違いないのに。
断るにしても、もっと上手で大人びた断り方があるに違いないのに。一人きりの湯船で、亜希は自分の物慣れなさにしゅんとしてしまったのだ。
夏は植物が一息に成長する季節だ。
結城の部屋のベランダ、そこで作った亜希の薬草園は、夏の強い日光を受けて緑濃く茂っている。夏休み中なこともあり、亜希は薬草たちの世話に精を出しているが、この薬草園の世話で悩み事があったので、ノエルに相談することに決めた。
「何を育ててるんだっけ。ローズマリーとセージ、ゼラニウムとペパーミントなんかがあったのは見たかな。その後、種類が増えた?」
日曜日の二十一時。イギリスにいるノエルとオンラインで会話をするのが恒例だ。あちらは十二時だ。
「ラベンダーとスペアミントと、ローリエとレモンバームが増えた。ラベンダーに花が着いた時期は、風が窓から入ってくるといい香りがして結城さんも喜んでくれてた」
亜希はカメラをオンにしたスマホを手にし、ベランダへと向かい、豊かに育った薬草園をぐるりと映して見せた。背の低い植物ばかりなので、膝の辺りまでしか高さはないが、どれも葉は色濃く、茎はしっかりとしている。
「ここは陽当たりがいいから、どれもすごく元気に成長してる。間引くのも可哀想だからこのまま育ててるんだけど、そろそろ限界かなって。だから兄ちゃんに、一気に消費する方法が何かあるか教えてもらいたいんだ」
「うん、上手に育ててるんだね。育てるのも大切だけど、薬草は使ってあげるのも確かに大切だ。そうだなあ、今からドライフラワーにして、うちの学院の秋季バザーにスワッグを作って出すといいよ」
「そうだ、にーちゃん出品してたよね。俺も子供の頃にバザーは連れて行って貰ったから、毎年人気だったの憶えてる」
「それと、亜希は無農薬で丁寧に育ててるから、食用にも使えるよ。ラベンダーはリラックスのためのハーブティとして有名だね。ストレスの多い生活をしてる人や、不眠症の人なんかによく勧められるよ」
ノエルはハーブの使い方をたくさん教えてくれた。
ハーブティにしたときの効能や、料理での使い方、熱湯でハーブの成分を浸出させて、掃除に使うのもいい。自然由来の虫よけのスプレーを使うことも出来る。
「そっか、ラベンダーはお茶にもなるんだ。結城さん、最近仕事が忙し過ぎてコーヒーを飲み過ぎって言ってたから作って出してみようかなあ」
「結城さんは? まだ帰らないのか?」
「うん、もう帰ると思う。最近ずっと遅かったから、今日はなるべく早く帰るって言ってた」
「なるべく早く帰る、で二十一時過ぎ、か。相変わらず忙しい人だ。結城さんとは? 仲良く出来てるのか?」
「ん? うん。まあ……」
亜希は口籠る。ノエルが苦笑した。
「何だ、今の間。また何か『ハンコウキ』で揉めたのか?」
「してない、『ハンコウキ』も、揉めたりとかもしてないけど……」
セックスの後にお風呂に一緒に入る、入らないで拒否をして、スケベ、オヤジっぽい、などと言ってしまった、とノエルに言えるはずもない。大好きな義兄だけれど、結城と恋人として交際している、と告白する勇気がない。きっと驚かせてしまうし、こんなにも離れているときにオンラインで伝えるのではなくて、顔を見て伝えたい。
結城への思いが真剣だからだ。言葉も、表情も、体から醸し出す気配も全部を尽くしてノエルに結城への気持ちを伝えたいと思う。
亜希の沈黙を見て、ノエルは違う解釈をしたようだ。また結城に『ハンコウキ』をして膨れているのだと思っているのだろう。
「分かった分かった。じゃあ結城さんと仲直りするためにもハーブを使って二人の気持ちを癒す方法を教えようか」
ノエルが最後に教えてくれたその方法を、亜希は目を見開いて聞いていた。これこそ、亜希が求めていた方法だった。
翌日の夕飯に、亜希はフレッシュハーブのチキン焼きを作った。ブラックペッパーと、塩味には岩塩を使ったのが正解だったようで、上出来の仕上がりだ。食後のハーブティーも用意しておく。
夕食のテーブルで、香ばしく焼けたチキンに舌鼓を打ちながら亜希は結城に話しかける。
「昨日、いつもみたくにーちゃんと話したんだけど。オンラインで、カメラをつけて」
「うん?」
「薬草の使い方をあれこれ教えて貰ってね、ベランダの、薬草園のハーブがすっごい育ったから、たくさん消費出来るいい方法を聞いてみたんだ」
「それでこのメニューか。さっきのチキンも香りが良くて美味かったし、このハーブティーも好きだな。夏場で暑いはずなのに、すっきりしてて飲み心地がいい」
「それ、ペパーミントとスペアミントのブレンド。それで、同じブレンドで入浴剤も作ったんだ。お風呂に入れたらミントの効能で肌がひんやりして、いい匂いがして夏場のお風呂にすごくいいんだって。暑さをすっきりさせてくれるお風呂になるって」
ノエルに教えて貰った通りの効能を話す。
ペパーミントやスペアミント、日本のハッカなど、ミント系の薬草には、夏真っ盛りの暑気にあたって疲労した体や心を鎮めて癒してくれる働きがある。 「今日も真夏日で一日暑かったよね。俺も薬草を摘んだり洗ったりで汗かいちゃって。だからあの、一緒にお風呂に入る?」
俯いて、もじもじと誘いかけると、結城は少し驚いたようで一拍の沈黙があったが、やが笑顔を見せてくれた。
「いいのか? 恥ずかしいから嫌だって怒ってたのに」
「……あのね、入浴剤を入れるときは灯りを消して入るといいんだって、にーちゃんが言ってた。視覚を塞いだら嗅覚とか触覚が強くなって、そうしたら、お湯の暖かさとか、薬草の香りをより強く感じるんだって」
一生懸命に伝える亜希に、結城が優しく微笑してくれた。
「そうだな。じゃあ一緒に入ろうか」
目の細かいタオルを用意して、摘んできれいに洗っておいたミントの葉を適量包み、麻紐でしっかりと括る。こぶし大の包みを作って、これを風呂に浮かべるとミントの薬草風呂が出来上がる。
「いい匂い。自分が育てた薬草のお風呂に入るってなんか嬉しい。世話をしたことが実った気がする」
清々しい、爽やかなミントの香り。ひんやりと清涼感があって、浴室がいっそう心地の良い場所になる。
入浴剤を浮かべた湯船の中、背中を向けて結城の脚の間に座り、亜希は両手で湯をすくう。手の中で、暖かいオレンジ色に揺らめいた。約束通り浴室の灯りは消し、結城のアイデアで、窓辺に非常用のキャンドルを二つ灯しているのだ。
「非日常な感じでいいな。確かにリラックスするよ、薄暗くていい香りがして、暖かい」
結城が背後から、ときどき背中にお湯をかけてくれる。セックスのときとは違う幸福感があった。心も体も許した人の肌に触れるって、すごく幸せだ。それに、何故か懐かしい気持ちがする。
「ノエルが羨ましかったんだよな」
結城がぽつりと言った。
「まだ俺達が高校生だった頃かな、あいつがよく言ってたんだ。弟の世話が楽しいって。弟を風呂に入れて、体中を洗ってから少し温めの湯船に浸からせる。一緒に歌を歌って、風呂上りは冷たいミルクを用意しておく。それだけでもうご機嫌で布団に入ってぐずらずによく眠ってくれるってさ」
「にーちゃん、そんなこと言ってたの?」
「食事をさせたり、風呂に入れたり、寝かしつかせたり。十も年下の義理の弟の面倒なんて大変じゃないのかって思ったんだけど、お前が可愛くてたまらないから、何をしてやっても楽しいって。それが何となく羨ましかったんだ」
確かに、ノエルと一緒に湯船に入った記憶がある。その日の出来事を一生懸命に話しながら、体を洗ってもらって、湯船に入った。湯船では百まで数えて温まるルールで、ノエルと一緒に一から百まで大きな声で数えたものだ。
まだ義父も母も生きていた頃だ。仕事で帰りが遅い両親に替わって、小学生だった亜希の面倒を見てくれたのは高校生のノエルだった。幼稚園や小学校に迎えに来て、食事を作ってくれた。
今考えてみたら、あの頃のノエルは今の亜希とほぼ同い年だったのだ。亜希は割合に大人しくて従順な気質ではあると思うが、十代の少年が子供の世話なんてきっと楽しいばかりではなかったのではないかと思う。それでも楽しい、と言ってくれたノエルに、亜希は申し訳なさとともに深い感謝を改めて感じた。
「俺は兄弟で一番下だろ。だから小さいのを世話をしたことがないんだ。正直、ずるいと思ってた。俺だってお前がチビの頃に一緒に住んで可愛がってみたかった。つついて甘やかして、そりゃあ可愛かっただろうなって思うんだ」
「……本気で言ってるの?」
「馬鹿なことを言ってる自覚はある。俺にはノエルに負けないくらいお前が可愛いから、あらゆる手段で可愛がりたいんだよ。それだけだ」
疲れているときには、きれいなものや可愛いものに触れていたいと思うのはごく自然なことだ。人間同士の醜い争いを傍で見る殺伐とした職業に携わっているからかもしれない。だから余計に、清潔な場所で、愛情の対象に大切に触れていると、心が浄化される。癒されると結城は言った。
「だからまあ、ちょっと恥ずかしいことくらいは我慢してくれよ。俺もお前を可愛がりたい。それだけなんだ」
「うん……」
亜希は素直に頷いた。そして、結城が自分の気持ちを率直に伝えてくれたから、亜希も自分の思いを伝えてみようと思う。亜希が一生懸命育てた薬草が、きっと力を貸してくれる。
「あのね、でもこの入浴剤、実はミントの他に、ローズマリーも足してあるんだ」
薬草の効能はよく知らない結城が不思議そうにしているのを感じる。亜希は一息に言葉を繋いだ。
「ローズマリーって、集中力を上げたりモチベーションを高めてくれる香りで、えーと……性欲を高めたりもするんだって。だから、あの」
このお風呂の後で、違う意味でも可愛がってもらえたらすごく、嬉しい。いっぱい。
気持ちを精一杯に伝えると、結城は微笑する。肩越しに目を合わせ、キスをして、亜希が一番欲しい時間をたくさん貰えたのだ。
おしまい