『苺と弁護士シリーズ。』
KindleDirectPublishing『恋の魔法に失敗して意地悪な弁護士さんに発情してしまう苺のお話』
の番外編になります。J-Garden53で、水瀬結月先生のスペースで無料配布をしていただいた小冊子に掲載した
ものを改めてアップさせていただきます。お楽しみいただけたら幸いです🍓
本編はこちらから どうぞ!
※本編には18禁表現が含まれます。未成年の方、性的表現が苦手な方の閲覧はご遠慮下さい。
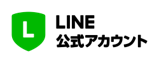



苺は今夜、どうしても眠れなくて困っているようです。🍓
パジャマ姿の亜希は、ソファの上でカモミールのハーブティーを飲んでいる。
眠れない、というので、さっき結城が淹れてやったものだ。亜希の義兄ノエルは薬草(ハーブ)の研究者で、亜希が現在暮らしているこのマンションにも様々な薬草が常備されている。
もうじき日付が変わる。明日、亜希は午前四時に起きなければならない。
「じゃあ明日、うちのマンションの玄関口まで迎えに来て貰えるんだな」
「うん、玄関に到着したら海斗がメッセージくれるって」
「俺も一緒に出て、安宗君のお父さんに挨拶するよ。一応、保護者だからな」
安宗海斗(やすむら かいと)、という名前は亜希の話にもよく登場するクラスメイトだ。彼の父親が、GWに上手く休みが取れたから、良かったら一緒に日本海にある離島に行かないかと誘ってくれたのだ。安宗とその父親、弟、そして亜希とクラスメイトがあと二人。バックドアにテントを連結させる仕様のキャンピングカーに乗り、キャンプや魚釣りをしながら島を一周する。
「魚が釣れないと、ごはん抜きかも知れないって。それから、途中で、天体観測所の近くに泊まるから、大型望遠鏡で土星の輪を観せて貰えるんだって。俺、望遠鏡なんて初めてだよ」
クッションを胸に抱き、頭をこてんと結城の膝に乗せる。
「そろそろベッドに行けよ。早く寝ないと寝坊するぞ」
「分かってるよー。でも全然眠たくないんだもん。小学生のときの運動会とか遠足のときの感じがこんなだったよ」
今日は旅行の前日というわけで、亜希の横顔からは興奮と緊張が伺える。それが過ぎるようで、眠れそうにない、とさっきからぐずり、寝室に行こうとしない。
「俺がいない間、ベランダの薬草園の世話、よろしくね。お水を日に一度あげるだけでいいから」
「分かってる、ちゃんとやっておくよ」
「明日、金曜日のいつものミーティングだけど、俺、にーちゃんと話せないね」
「時間になったらお前もその場でカメラをオンにしたらいいけど、旅行の最中にそこまですることはないよ。ノエルの都合がつけば別の日だって構わないんだから」
「うん………あー、どうしよう。ほんと全然眠れそうにないよー」
今眠っておかないと日中眠くなったり疲れやすくなったりでせっかくの旅行を楽しめない。しかし興奮して眠れない。
旅行をこんなに喜ぶのなら、結城が連れて行ってやりたかった。しかし担当している係争がちょうど山場だ。クライアントの予定が最優先の結城の職業上、GWだからだと好きに休暇をとることは出来ない。
寂しいような気持ちを誤魔化すため、結城はもう一度笑って、持っていたマグカップをテーブルの上に置いた。
「じゃあ眠れるおまじないをしてやろうか。前にノエルに聞いたことがある」
「おまじない? 兄ちゃん直伝? 眠れるの? だったらして欲しい」
がばっと体を起こして結城の顔を覗き込んで来たので、分かったと言って結城は亜希の右の頬にキスをした。それから左の頬。唇にも軽くキスをする。
亜希はきょとんと結城を見上げた。
「ほんとに、にーちゃんがこんなこと言ってたの? あちこちにキスするので、眠れるの?」
「そう。あいつは薬草だけじゃなくて、魔法やおまじないにも詳しいだろ。両頬と、唇と、両手のひら―――それから臍」
左右の手のひらに順番にキスをして、パジャマの上着をめくり、臍にも軽く唇で触れる。
「………やっ! くすぐったい」
亜希は大笑いしていたが、やがて息を詰める。結城が下肢へと体をずらし、亜希のボトムのゴムに指をかけたからだ。それを引き下ろし、淡い下栄えの陰に隠れていた幼い性器をそっと指に取る。
「………してくれるの? だって、明日早起きだから絶対ダメって言うと思ってた」
「そうだな、そっちは旅行が終わるまでお預けだ。でもこれはよく眠れるおまじないだ」
「んっ……」
まだ力ない性器の先端にキスをすると、亜希が小さく息を呑み、腰を弾ませた。以前、結城がケアして「大人」の形になった性器は、何度もキスを繰り返すうちに小ぶりながら血の気を漲らせ始める。その苺色の丸い先端を、唾液で濡らした唇でそっと挟む。
「…………………あっ、あ、ゆーきさ……」
ちゅ、ちゅ、と音を立てながら、何度も軽い口づけを繰り返すと、透明な雫が溢れ出して茎の部分を伝い、滑り落ちて来る。その潤いを潤滑剤にして手のひらで上下に扱き立てる。足の付け根や会陰に優しく舌と唇をそよがせ、少し焦らしてから、亜希を口腔にすっぽりと深く含んだ。
「や、ぁん………っ …………………!」
唾液を絡ませながら、性器の全体を唇で扱く。足の間で張り詰めている柔らかな袋は手のひらで揉みしだき、射精を促す。悩ましいフェラチオに、亜希は両膝を立て、ソファに踏ん張るように快感を堪えている。
「はあ………、は、ぁ…………」
口腔から亜希をいったん解放すると、しなるほどに勃起した性器は健気に打ち震えていた。しとどに濡れた窪みを指腹で前後に擦り、悪戯をする。くちゅくちゅ、という水音に、亜希は恥ずかしがり被りを振った。
「………やっ、ん、だめ……っ」
「我慢するなよ、早く眠れるおまじないだって言ったろ。すっきりして寝ちまいな」
「んっ、んん………、これ、ほんと、に、おまじない、なの……?」
「もちろん。今度ノエルに聞いてみな」
そんなこと、聞けるわけない…、と震える細い指が、結城の髪に触れる。宥めるようにその指先にも軽くキスをしてから、もう一度亜希を口に含み、やや強めに吸い上げた。薄い皮膚が張り詰めて、感じ易くなっているくびれをぐるりと舐め回す。
「……………や、………やぁ、ん、ゆうきさん、ゆーき、さ………―――」
恥ずかしそうに結城を呼ぶ、その度にとろり、とろり、と間欠的に先走りが溢れる。きゅうっと締め上げてやると、亜希はたまらずに結城の髪を掴み、しなやかに背中を仰け反らせた。
「――――――あぁ………………………っ!」
口の中で、亜希が打ち震え、熱い体液が勢い良く射出される。最後の一滴まで絞り取るように、結城は亜希をきつく吸い上げた。
「う、んっん………」
あえかな声と共に、亜希が脱力する。結城はすべてを飲み下し、手の甲で唇を拭って、肩を上下させている亜希の頬に優しくキスをした。ティッシュペーパーを抜き取って汗や色んな体液を丁寧に拭う。
極まったばかりの敏感な体を無闇に刺激しないよう、そっとパジャマを元通りに直してやり、背後から抱き締める。二人でソファに横たわった。
「気持ち良かったか?」
「…………ん」
小さな声で答えて、恥ずかしそうに結城の腕に鼻先を押し付けている。交際が始まって五か月、もっと過激な行為もたくさんしているのだが、未だにセックスには躊躇いと羞恥を感じているらしい。
それも仕方のない事だ。亜希の初恋は、魔法が契機で始まったのだ。現実や日常とは違う、童話のような恋だ。そして結城の恋人は、どうしようもなく幼い。だから、どんなときでもゆっくりと歩調を合わせてやろうと思う。
「………あした、ミーティングのとき、にーちゃんに……旅行のお土産買って来るって、言っておいてね。次会ったとき、渡すって」
「分かった、伝えるよ」
「きれいな景色や美味しい食べ物、たくさん撮って、メッセージで送るからね。結城さんが、一緒に旅行してるみたいに思うくらい、たくさん」
一緒に旅行をしてるみたいに。ずっと一緒にいるみたいに。
さっきのハーブティーの効果か、「おまじない」が効いたのかは分からないが、やがて亜希の呼吸が深くなる。目を開いている感覚が間遠になり、すうー…と長い吐息が聞こえる。
結城は微笑して体を起こす。亜希を起こさないよう、横抱きにしてソファから抱き上げた。亜希の部屋へ向かい、ベッドに入れてやる。
腕の中に容易く納まるこの華奢な感触が愛しいけれど、幸福な思い出をたくさん作って成長して欲しい。そう思うのもまた本当なのだ。
「気を付けて行っておいで」
額へのキス。おまじないの、一番最後「いい夢を」
のキスを落として、結城はベッドサイドの灯りを消した。
「それで、亜希は午前四時に起きて元気に出発して行ったんですね」
「ああ、安宗君のところがうちの前まで迎えに来てくれて。キャンピングカーが大きいってずいぶん興奮してたよ。さっきは皆で協力して、海辺にテントを張ってるって動画が来てたろ」
「ずいぶんはしゃいでましたね。少し見ない間に背も伸びたんじゃないですか?」
目の前に開いたノート型PCの画面の中でノエルが笑っている。
定例となっているミーティングだ。日本は二十二時、ノエルがいるイギリスは午前十時だ。金色の髪が映える美貌に、朝の光が実に似合う。
ノエルが日本を離れることになった四か月前、週に一度は必ずこうしてオンラインで近況を報告し合う、そういう約束を交わした。
「俺が連れて行ってやれたら良かったんだけどな。今抱えてる案件がちょっとややこしくて、連休中も東京を離れるのはどうにもな」
「いいえ、先輩は仕事を最優先にして下さい。亜希も同い年の友達と遊ぶことも大切ですし、今回の機会は俺にもとても有難いです」
「あいつが旅行から戻ったら、翌日内に安宗君のところには電話をかけてお礼を言っておけばいいんだよな?」
「そうですね、俺のときは後日、お菓子や名産を送らせて貰っていました。現金だとなかなか受け取っていただけなくて。一緒だったお友達のお家にもお声がけしておくといいと思います。何かとお世話になっているはずなので」
「そうか、なるほど」
保護者というのも全方位に気を使って大変なものだな、と改めて思う。特にノエルは自分も学生の頃から、亜希の保護者でもあったのだから、本当に大変だっただろう。もっともノエル当人は、「可愛い弟のためなら大した苦労でもなかった」と笑って話す。
この義兄弟ときたら呆れるほどに相思相愛で、亜希は言葉にはしないが、やはりオンラインだけでなくリアルで会いたいだろうと思う。今年受験生である亜希の成績に問題がなければ、夏休みにイギリスに連れて行こうと結城は考えている。そのために、今のうちに可能な限り仕事を片付けておきたい。
夏のイギリスで兄と再会する亜希の笑顔を思うと、結城は今から微笑ましくなるのだ。
「結城さんは明後日まで一人ですね。どうです、久しぶりに伸び伸び出来ていますか」
尋ねられ、結城は困惑する。確かに一人、というのは自由ではあるし、以前はそれが心地良くてならなかったのだが。
「静かだよな。今日も無意識に、あいつが帰って来るのを待ってたよ。帰って来たら、鍵を開けてやらないとって。いつの間にか俺も過保護なにーちゃんみたいになってるな」
「仕方ないです、亜希は可愛いですから。どうしたって過保護になるんですよね」
なんという兄バカなのだろうかと改めて思ったが、黙っておく。ノエルに呆れていられる立場でもなくなってきた自覚があるからだ。
そして亜希を途方もなく可愛い、という思いが、保護者としてだけのものではない、ということは必ずノエルに話さなくてはならないだろう。無論殴られる覚悟はあるし、土下座も厭わない。ただ亜希に泣かれるかも知れないと思うと、やはり胸が痛む。
ふと青い爽やかな香りがして、結城は顔を上げる。開け放しにしていたベランダとの掃き出し窓から心地いい夜風が吹いていた。夏の湿気を孕んだ風が、亜希が丹精している薬草園の香りを運んでくれたのだ。それは亜希の匂いとよく似ていた。
「まあ俺は、あいつが帰って来るまであんまり部屋を散らかさないようにしておかないとな。帰って来るなり叱られたんじゃ保護者失格だ」
「結城さんはきれい好きだし、もともと一人暮らしをされてたんだからそんなに散らかしたりはしないでしょう」
「そうは言っても、あいつは整理整頓がとんでもなく上手だからな。それに一緒に暮らし始めたら分別だとかゴミ出しだとか、細々と引き受けてくれてたから、つい甘えてたよ。亜希も大学生になったら友達と出かけることも増えるだろうし、自分がいなくても大丈夫だって見せておいてやらないと」
それを聞いたノエルは、何故か黙って微笑している。画面越しの美貌を、結城は軽く睨んだ。
「何だ、そのムカつく感じの上から目線の笑顔は」
「まだまだ、亜希の扱いは俺の方が上級者だなって思っただけです」
「ふうん? じゃあご教授願おうか」
結城が請うと、ノエルはにっこりと笑った。
三日後、亜希は笑顔いっぱいで帰宅した。
リュックを背負い、両手には大きなビニール袋を携えている。帰路の途中で連れて行って貰ったという「道の駅」
で買った新鮮な野菜や果物をたくさん持ち帰ったらしい。
「すっごく楽しかったあ! 全部楽しかったけど、天体観測、すごかった! 俺、あんなにたくさん星を見たの生まれて初めてだよ。空が真っ白に光ってるんだ。車の中で寝るのも、テントで寝るのも面白かった!」
よほど楽しかったのだろう、玄関先で靴を脱ぎながら、旅の記憶を一息に語る。しかしリビングに入った途端、亜希は呆気に取られて目を見開いた。
「ナニコレ……」
茫然と部屋を見回す。三日間、リビングもキッチンも、一度も掃除をせずにおいた。
服は脱ぎ散らかし、読んだ本は読みっぱなしだ。茶碗も洗わず、前の皿はテーブルに放置して新しい皿を使った。この部屋で寝起きをしたので、枕やタオルケットも散乱している。不自然でない配置にするのになかなか骨を折ったのは内緒だ。
「何で、何で三日でこんなに散らかるの!?」
「あー…お前が出掛けてから急な訴訟が入って、ちょっとバタバタしたんだよなあ」
亜希はキッチンを覗き込み、そこでも悲鳴を上げた。
「あっ! 生ごみも出してない。変なにおいしてる!」
「薬草園にはちゃんと水をやってたよ」
「それはうれしいけど、結城さんのごはんは? ごはんはちゃんと食べてたの?」
亜希に食事の心配をされることになるとは、と結城は感慨深い。
「ああ、もちろん。お前がきちんと用意してくれたから助かった」
「ほんと? 何が美味しかった?」
「ビーフシチューだな。丸ごと入ってた玉ねぎがくたくたに煮込まれてて甘くて美味かった」
「あのシチュー、海斗のパパに作り方教えて貰ったんだ。玉ねぎがお肉を柔らかくしてくれるんだよ。多めに生クリームを入れたから、味がまろやかになって……じゃなくて! 俺がいないとダメとかダメじゃん!」
「ああ、まったくだ。お前がいてくれないとどうにも生活が回らない。すごく困ったよ」
両腕で作った輪の中に亜希を収め、率直に告げる。亜希はこちらに向き直った。
―――自分がいなきゃダメだって、しっかりしなきゃって思わせて成長を促すのも、きっと大人の仕事なんです。
先日のミーティングで、ノエルはそんな風に結城に言った。成長のためだけではなく、結城の生活には亜希が必要なのだと伝えることは、今の亜希にとってとても大切なことだ。
ベランダの向こう、亜希の薬草たちの気配を感じる。彼らも、亜希の帰宅を喜んでいるのが分かる。
亜希はちょっと上目遣いになり、唇を尖らせている。ちらちらと結城を見上げながら、結城に尋ねた。
「ほんと? 俺がいなくて、困った?」
「ものすごく困った。何回かSOS出そうと思ったくらいだ」
「……ほんとにほんと?」
「ほんとにほんと」
笑って言って、亜希を抱く腕に力を込める。亜希は嬉しそうに頬を結城の胸に寄せた。
「俺も、旅行はすっごく楽しかったけど、早く結城さんに会いたかった」
そうか、と微笑して結城は亜希にキスをする。何の屈託もなく、素直に思いを打ち明ける恋人がただ愛しくてならない。
結城をいつでも幸せにする魔法使いはまだ幼い。だからこの腕に抱いて、恋ごと大切に守っていくのだ。
おしまい