『恋人としくじりロリポップ』
ルチル文庫『だんだんもっと、甘くなる』(イラスト:サマミヤアカザ先生)
の番外編になります。J-Garden53で、水瀬結月先生のスペースで無料配布をしていただいた小冊子に掲載した
ものを改めてアップさせていただきます。お楽しみいただけたら幸いです🍓
本編もぜひよろしくお願いします幻冬舎コミックスHPへ
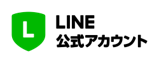


愛の存在を決して信じようとしなかった。それはきっと、愛がもたらす歓びを知った後で、失うことがただ、恐ろしかったからだ。
金曜日の夜二十時。カフェでのアルバイトを終わらせた恵を、清名は自ら運転する車で迎えに来ていた。
仕事が終わった後、金曜日のデートだ。いつもなら、年下の恋人は元気いっぱい上機嫌で現れるのだが、今日、車に乗り込んで来た恵は何故か微妙な顔をしている。腕に、一抱えもある重そうな紙袋を抱いていた。
「ずいぶんな荷物だね」
興味深い思いで清名は尋ねる。恵がすることは、いつでも清名には予測不能だ。
「バイトの前に、うちの近所の商店街を通ったら福引やってて、ガラガラ回したら当たったんだ。四等ロリポップキャンディの詰め合わせ五十本」
「どうして渋い顔をしてるんだ。君は甘党だから嬉しいんじゃないのか?」
「そりゃあ好きだけどさ、甘いもの。ロリポップは色んな味があって楽しいし」
苺味が一番好き、と言って一本取り出す。それを指先でくるくると回して見せる。細いプラスティック棒に、カラフルなセロファンで包まれた丸いキャンディが取り付けられている。その形状を、困惑した表情で見つめている。
「えーと、思い出すじゃん…あのときの」
「思い出す? 何を」
「ええと、だから俺、前に、失敗して、清名さんをアパートに呼んだことあったよね? 助けてって」
「失敗?」
「だから、お尻だけで、あの、……自分で訓練するために俺が、ロリポップの形のおもちゃを買って、それが不良品で、一人で使ってて、事故ったことがあったじゃん」
あのとき、助けて欲しいと連絡を受けて大慌てで恵が1人暮らしをするアパートに駆け付けた。気が強い恵が、どうしたらいいのか分からないと泣きべそをかいてベッドの上に蹲っていたことを思い出す。
思い出して、思わず吹き出してしまった。それでもちろん、清名が同じ出来事を思い出していたことに恵も気がついたようだ。こちらに身を乗り出して、ぽかぽかとこぶしで肩口を叩く。
「もー! ひどいよ、絶対分かってたくせに!」
「ごめんごめん、その顔を見てるとついからかいたくなった」
「笑いごとじゃないよ、あのとき本当に怖かったんだから。正直、あれから棒付きのキャンディ見るのも怖くて食べられなかったんだよ!?」
「そりゃあ気の毒に。でも君がそうやって体を張って頑張ってくれたおかげで、仕事は順調だし兄たちとも仲良くやってるよ。以前よりは」
それを聞いて、それこそキャンディみたいに大きな瞳が揺れた。
清名の生育環境と、その後の家族たちとの付き合いについて、言葉にしないまでも恵が心配していることを清名も感じている。
「ほんと…?」
「本当。ところで、その五十本の中に君がおすすめの苺味は入ってる?」
「ん? うん。えーと、苺味は……」
紙袋の中を探り、一本を取り出した。ピンクに赤の模様が入ったセロファンに包まれた、棒付きキャンディ。清名はそれを受け取った。
「これは俺がいただくよ。俺が食べて平気なのを見れば、君のトラウマも晴れるだろう」
「清名さんが棒付きキャンディ食べるの?」
「君のトラウマ解消に一役買えるならね」
そう言ってセロファンを外し、咥えた。懐かしい味がする。子供の頃、子供向きの菓子を食べさせて貰った記憶はないのに、何故か懐かしい、と思う。
本当に不思議だ。恵といると、時々知らないはずの感情に駆られることがある。恵がこれまで受けて来た愛情や優しさ、美味しい記憶、楽しい気持ち、幸福なそのすべてを分け与えて貰える気がして、だから清名はどうしようもなく、この年下の恋人が「愛しくて」ならない。その感情を、今はもう、ただ素直に受け入れている。
キャンディを口に咥えてエンジンをかけると、恵が楽しそうに笑う。
「なんか、清名さんがキャンディ食べてるの可愛いかも」
それを聞いて一瞬むせそうになる。誰より可愛らしいと思う恋人に可愛い、などと言われると困惑してしまうが、恵が楽しそうなのでまあいいかと受け流しておく。
「さあ、じゃあトラウマ克服のお祝いをしようか。少し遠出になるけど、君が食べたいって言ってたミラノ風ピザを出す店があるんだ」
「やった、生ハム大好き」
恵がいっそう笑顔になる。
「ホールケーキとかピザとか、丸い食べ物って幸せそのものって感じがするよね」
だから大好きな人と一緒に食べると、いっそう美味しい。
清名は微笑してアクセルを踏み、車を発進させる。恋人の、ささやかな言葉のすべてが愛しいと思う。
それが「愛」という存在が、自分の中で育ち始めている証であればいいと、清名は考えている。